

#4公認会計士
×教育
学校法人田中学園 清和幼稚園 経営企画担当/
事業構想大学院大学 客員教授
結城秀彦さん

自ら学び本質をつかむ
未来を担う教育を持続可能に
テクノロジーが加速度的に進化し、AIが日常に溶け込みつつある今。私たちは何を学び、どう生きていけばいいのでしょうか。
人間にしかできない思考力や想像力、そして他者と関わる力――。そんな『人の力』を育てるのが教育なのだとすれば、今こそその本質に立ち返るべきなのかもしれません。
今回ご登場いただくのは、大手監査法人のパートナーを退任し、現在は幼稚園と大学院という2つの教育の場で奮闘する結城秀彦さん。
子どもたち、そして社会人の学びに関わる日々の中で見えてきた『未来につながる教育』について、お話を伺いました。


大切なのは、自分の頭で考える力
『自ら学ぶ』スタイルで
公認会計士に
結城秀彦さんが公認会計士を目指したのは、大学4年の秋、卒業まで半年を切った頃のことだった。それまで公認会計士という職業について、深く考えたことはなかったという。
「就職活動を始めてみたものの、自分を語れるような経験も能力もないと感じてしまって。何かひとつでも身につけてから社会に出たい、と思ったのがきっかけです。たまたま父の関係で公認会計士の方とお話しする機会があって、それが刺激になりました」
未知の分野に触れる新鮮さとともに、働かずに勉強していることへの引け目も感じていたという。そこから集中して学習に取り組み、卒業翌年には試験に合格した。

結城さんが一貫して大切にしているのは『自ら学ぶ姿勢』だ。これは、幼少期から親に言われてきたことでもあった。
「学校で教わったことがそのまま身につくわけじゃない、という考えで育ちました。ずっと自分で勉強するというスタイルだったので、それが公認会計士試験でも活きたと思います」
監査以外の幅広い業務も経験
1986年、結城さんは現在の有限責任監査法人トーマツに入所。組織内に壁がなくフラットな運営に惹かれたという。以来38年間にわたり監査業務を中心に、多様な領域に携わってきた。
その間、 アメリカへの研修、 ドイツ駐在も経験。その後は内部監査の支援や内部統制に関する研究にも力を入れていた。
監査法人の外でも、日本公認会計士協会の監査・保証業務やテクノロジー関連の役員、公認会計士試験委員なども歴任している。
「監査だけでなく、保証業務やテクノロジー、管理会計といった分野にも関わってきました。たとえば監査以外の保証業務といった新しい領域にも、国内の実務指針づくりの段階から携わりましたし、コロナ禍にはテクノロジーを使ったリモート監査の仕組みを検討することもありました」

マニュアル室業務で
たどり着いたこと
結城さんが長年にわたり関わってきたのが『マニュアル室』での業務だ。監査メソドロジーやコンテンツの策定、それを現場で適用するための支援が主な業務内容である。
「マニュアルや調書の様式はソフトウェアやポータルサイトを通じて個人に提供するので、そのための仕組みも勉強させてもらいました。
またこれらを現場で正しく使うためのガイダンスを作ったり、うまく適用できないという相談に応じることも重要な仕事でした」
20年にも及ぶ期間、マニュアル室の業務を担った末、結城さんはひとつの結論にたどり着いた。それはある意味マニュアルを知り尽くし、あらゆるケースを目にしたからこそ見えてきたものなのかもしれない。
「何だか矛盾を感じるかもしれませんけど、最終的には思ったのは『マニュアル人間は役に立たない』ということでした」

マニュアルに書いていない
行間を読む
「ある方法論を現場に当てはめようとしても、条件や状況によってはそのままでは使えないことが多いです。自分で調べたり工夫することができなければ業務には活かせません」
マニュアルやルールは一定の指針にはなるが、現場の実情は常に多様で複雑だ。そうした場面では、基準に従うだけでは対応しきれない。
「過去の事例を調べて、似たものがあったからと同じように処理すればいいと考える人もいます。ですが、データベースをひたすら読み込むことよりも、そもそもルールが何のためにあるのか、どういう趣旨で作られているのかを理解することのほうが大切です。
つまりマニュアルの『行間』を読み取る力、自らの判断でその行間を埋めていく力こそ必要なのではないでしょうか」

※監査法人に勤務していた頃の結城さん
ルールの先を想像する力とルールの根本を疑う力
マニュアルを過信せず、自分で考えることの重要性。そのベースにあるのは、想像力と懐疑心だと結城さんは話す。
「このルールを現場で使ったらどうなるか?と想像してみる。あるいは、そもそもこのルールは正しいのか?と疑ってみる。そうした姿勢がないと、本当の意味での対応力は身につきません」
現代はコンプライアンス重視の風潮もあり、ルールに縛られる場面も多い。だが、時にはルールを見直す必要もあるはずだ。
「この20年くらいで、ルールから一歩外れて何かを試すということが難しくなったと感じます。でもルールが現実に合わないこともありますし、試してうまくいかないリスクばかりを気にしていたら、新しいことに取り組むのは難しいですよね」
想像力も懐疑心も、根本にあるのは『自分の頭で考える力』。その力を若いうちから育てていくにはどうしたらよいのだろうか。
「教わるだけでなく、自分で調べて考えてみること。それが重要だと思います。知識を得たら、実際に仕事の中で使ってみる、誰かに向けてアウトプットしてみる。そうやって学びを深めていくための能力開発にも力を入れていく必要があります」
そして最後に、そんな力を養うためのシンプルかつ有効な方法を教えてくれた。
「読書はおすすめです。物語を通じて誰かの人生を体験することで、自分の想像力も育ちますから」
持続可能な幼稚園経営を目指して
広々とした園庭が魅力の清和幼稚園

2024年3月に監査法人のパートナーを退任した結城さんは、現在、千葉県船橋市にある清和幼稚園の経営企画に携わっている。
1971年に創立されたこの幼稚園は、地元でも知られた存在だ。その最大の特徴は、なんといっても広々とした敷地。エントランスからは想像できないほど自然豊かな園庭が奥へ奥へと広がっている。いったいどこまでが幼稚園の敷地なんだろうと驚いたほどだ。
園内の自然を活かした取り組みも多く、「この前は園庭で収穫したビワを私も食べたんですよ」と、うれしそうに写真を見せてくれた。
自ら志願して経営企画に参画
結城さん自身は、この幼稚園の卒園生ではない。しかし、創立者である田中恒春氏(前理事長)の中学時代の教え子であり、2002年頃から評議員として関わってきた。
「2021年に50周年記念式典がありまして、挨拶の機会をいただいたんです。そのとき改めて、ここまで続けてこられたことのすごさを実感しました。周囲の環境もずいぶん変わって、宅地化も進んでいるなかで、こうした場所を守り続けてきたのはすごいなと」
創立当初、女性の活躍の場として幼稚園を作ったという田中先生の志を聞き、結城さんは『次の50年』の担い手になろうと決めた。
「100周年を迎えられるように、これからの経営を支えたいと思って、ある意味押しかけで経営企画をやらせてもらうことになりました」


困難な時代に選ばれる園を目指して
清和幼稚園のある地域では、行政による保育施設整備が進み、預け先の選択肢が豊富になっている。保護者のニーズは預かり時間の長さに集中し、幼稚園も対応を求められるようになった。
「近隣に保育園が非常に多い。清和幼稚園では朝7時半から18時半まで預かり保育をやっていますが、どうしても駅から少し距離があるので、そこがネックになることもあります」
こうした環境のなかで、持続的な園運営をしていくためには何が必要なのか。
「まずは園児の確保。それと並行して、保護者の期待に応える教育を続けること、コミュニケーションをしっかり取ること。さらには幼稚園で取り組んでいる教育内容をもっと発信していくことも大事だと思っています」

園児確保に向けた経営戦略
「教育は園長先生をはじめとした先生方が担ってくださっているので、私はその土台となる経営面を支えています」
清和幼稚園は私学振興助成法に基づく公認会計士の監査対象となっているが、これは他の公認会計士が担当している。結城さんは監査法人での経験を活かして経営企画に取り組んでいる。
「収支計画や予算の管理体制、業務プロセスの見直しなどをやっています。損益分岐点を試算したり、地域に入園対象の子どもがどのくらいいるかといったデータを使って、園児募集の方針を考えています」

この1年でいくつかの取り組みも始めている。
「入園時の一時金について、費用の内訳を明確にするため『緑のお庭協力金』という名目を設けました。園庭の維持管理にどうしても費用がかかるので、ご理解いただきたいと思って」
また、限られた人数で事務仕事を行うための業務効率化にも取り組んでいる。まだ紙や手書きが多く残る業務を見直し、デジタルツールの活用を検討している。
「放課後の預かり保育の申し込みも、現在は紙や電話対応が中心。それを連絡用アプリと連携して効率化できるように、スプレッドシートを活用して仕組みづくりをしているところです」

公認会計士として培った力を
活かして
園児募集に向けた取り組みとして、チラシの配布やポスターの刷新といった広報活動を進めている結城さん。今後は、幼稚園で行っている教育活動と目的を『見える化』し、保護者や地域により分かりやすく伝えていくことが重要だと考えている。
教育、広報、保護者対応などの活動と目的を整理し、どう実行していくかを可視化することで、園の強みや取り組みの方向性を関係者全体で共有しやすくなる。
こうした取り組みを進めるためには、監査法人時代に培った『段取力』が活きていると結城さんは言う。
「プロジェクトをどのように進めていくかを考える力、いわばプロジェクト・マネジメントの力は、監査業務でも必要とされる能力でした。どこで誰が何を担当して、どう連携するか。その計画を立てる力は今の仕事でも求められています」
さらに、その段取りを現場で確実に進めるためには、内部統制の考え方も役立つ。
「例えば業務の進捗が確認できたり、自分が介在しなくても業務が回るようにしたり。そんな仕組みを作る力も今の業務に活きていると感じます」

その学びは自分の人生にどう関わるのか
独自のファイナンス論を講義
結城さんは現在、大学院の客員教授として、東京・南青山にある事業構想大学院大学で教壇に立っている。この大学院は、社会人が自身の事業構想を立て、その計画を実行につなげていくことを目的とした教育機関だ。
結城さんが担当するのは『事業構想のためのファイナンス』。自身が長年取り組んできた監査や会計の世界とは少し異なるアプローチだ。
「この大学院ではまず、どんな新しい事業を生み出すかという『発着想』を重視します。そこから事業構想を構想計画として形にしていく段階で、どう人やモノを調達するか、そのためのカネ(資金)をどう確保するかといった点で、ファイナンスが必要になるんです」
講義では、一般的な金融技術や専門家向けの内容というより、院生が立案する構想計画の実現に直結する実践的なファイナンスの考え方を伝えている。

『なぜファイナンスを学ぶのか』を考える
講義を通じて結城さんが感じるのは、院生の多くが会計理論やファイナンスに触れるのが初めてだということ。中には、なぜこの分野を学ばなければならないのかが分からず、講義内容に戸惑う人もいる。
「日本ではこれまで会計教育が体系的に行われてこなかったこともあって、社会に出てから『思った以上に会計に関わる場面がある』と気づく人が多いんです。最近ようやく学習指導要領解説にも会計が取り入れられましたが、今後の会計教育の広がりに期待したいですね」
そうした背景を踏まえ、結城さんが重視しているのは、知識の使いどころを伝えることである。
「ファイナンスの技法や考え方など個々の論点を細かく解説するよりも、『なぜこれを学ぶのか』『自分の構想とどう関係するのか』が大事。特にこれまで会計を学んでこなかった院生には、この辺りに重点を置いて講義しています」
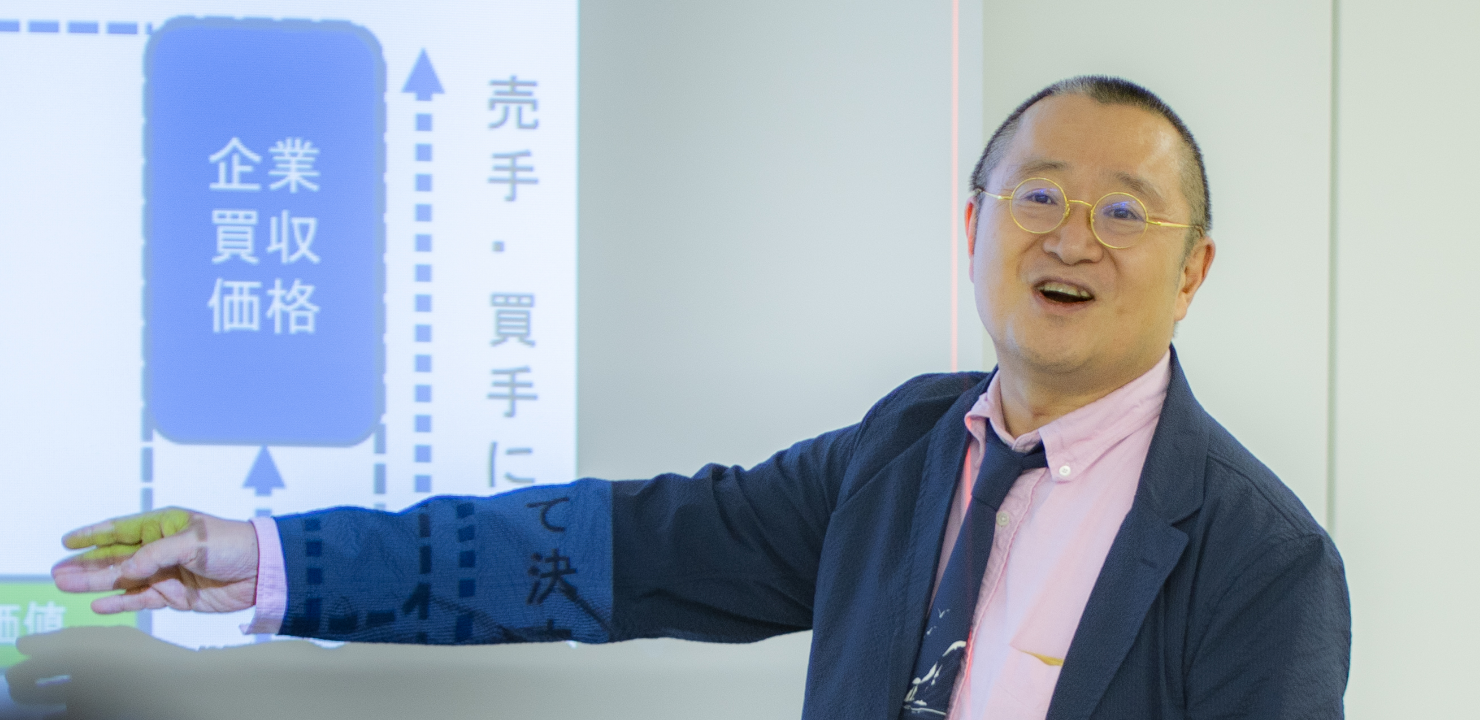
学びを『自分ごと』にする
幼稚園と大学院という異なる教育現場に関わってきた結城さん。何かを学ぶ上で大切にすべきことについて次のように語ってくれた。
「『なぜ学ばなければならないのか』を自分でしっかり考えることが大事です。自分の人生や仕事とどう関わるのかが分からないと、学ぶ意義が見えてこないんですよね」
実は、結城さん自身も大学時代は講義にあまり出席せず、学びに身が入らなかったという。
「結局、勉強していることが自分にどう関係するのか分からないと、興味が持てないんですよ。何かを覚えるだけでは学んだことが活かせないし、応用もきかない。そういう意味で、学ぶ目的や意義がとても重要だと思っています」
学びの出発点は、身近な疑問や興味から。結城さんは、好奇心や探究心こそが、学びを深める原動力だと語る。

未来につながる教育を
「教育は、卒園生や卒業生が社会に出てからどう活躍するかによって、その真価が問われるものかもしれません」
結城さんが経営支援を行う清和幼稚園には、教員として戻ってきた卒園生が7名もいるという。幼い頃に学んだ場所で、今度は教育者として次の世代を育てている。
「こうやって学びが受け継がれていく姿を見られるのはうれしいですね。この先も未来につながる教育を大切にしたいと思っています」

大学院では、院生がそれぞれの事業構想を実現すべく奮闘している。しかし結城さん自身は、必ずしも強いリーダーシップだけを求めてはいないという。
「『自分で何かやりたいことを見つけるべき』とか『リーダーにならなきゃ』とか、そういう強烈な想いを持たなくてはいけない、とまでは思っていないんです。
どこかの職場に就いて日々の業務をする中で、『この仕事にはどんな意味があるんだろう』とか『何を学んだらもっと良くできるか』と考えることができるだけでも、その人の可能性は広がっていくはずですから」
そして、最後に結城さんはもう一度、好奇心と探究心の大切さに触れた。
「何かに興味を持ち、調べて、自分で考える。そういう経験が、人の判断力や行動力につながっていく。幼稚園でも大学院でも、そうした機会を提供できる教育を目指していきたいですね」

SDGsゴールを目指す人を側面からサポートする
最後に、SDGs達成に向けて公認会計士がどのように貢献できるかを伺った。
「直接ゴールに関わるのではなくても、ゴールを目指している人や組織を側面から支援する形で、十分に貢献できると思います。
例えば学校法人の監査に関わっていれば、間接的にSDGsのゴール4『質の高い教育をみんなに』の達成を後押ししていることになりますよね。
それに、公認会計士として積み重ねてきた知識や経験は、他分野でも応用できることが多い。自分の業務の枠を超えて広がりが生まれれば、SDGsへの貢献の可能性も広がっていくはずです。
ぜひ、これまでの経験を活かして、新しい挑戦にもつなげてほしいと思います」
